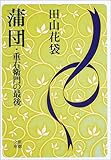私は物語も伴ばを過ぎるまで、本書が翻訳だと思っていました。
ちょうど背中にあたる部分にタイトルが白抜きで書かれています。
とてもインパクトがあります。
帯がその小説の中味を正しく伝えていることは少なく、大概帯には「いい意味で騙される」ことが多いのですが、いい意味だからと言って人を騙していいわけではありません。
読後感が良ければ良いほど帯の残念さ加減には腹が立つことが多いです。
表紙のインパクトと小川洋子の名前で買うことに決めました。
サリマが追い立てられるようにしてここにやってきてから、しばらくになる。
あちらでは人々がいがみ合い殺し合っていた
小説は、夫が辞めたスーパーマーケットの精肉部門でサリマが働き出すところから始まります。
それが人種のるつぼといわれる場所であったら、肌の色や言葉の違いでこれほど苦しむことはなかった。
夫から常にバカにされ、おおよそサリマは自尊心とは遠い存在のようです。
手紙を書いている主のことも、ジョーンズ先生が何者なのかも、小説の中で詳しく説明されることはありません。
しかしこの手紙は、ちょうどシ一ルや絆創膏のライナーのように、この小説が私達の心にぴったり貼られる手助けをしてくれます。
不思議な構成の小説です。
生き、生活するための言語として、英語を学ぶのです。
それは、そこで生きてゆこうという決意そのもののようです。
夫は女はバカだバカだと言い続けた
だから自分のことをバカだバカだと思い込んでいたけれど、いまは肉だって魚だってきれいに捌ける。
いままで知っている苦しみはおそらく、自分がいかに駄目な人間かと思い知ることだったけれど、そんな自分にいつまでも馴染めなかった。
そこでサリマは二人の女性と知りあいます。
1人は地元の男性と結婚して30年になるイタリア人女性、サリマはオリーブと名付けます。
もう1人は大学で研究をする夫に従って当地に来た日本人女性。ハネリズミと名付けます。
サリマを含めたこの3人がこの物語の主要な登場人物です。
サリマは彼女らの雑談に耳を傾けます。
彼女らの会話は、どこへ行って何をする、どこで何を買う、そんな他愛のない会話です。
しかし、故郷を焼け出されてここに辿り着き、生活のために必死に働くサリマには別世界に感じます。
xxに行けば、OOが手に入る。そんな単純なことが話題になって女たちを喜ばせているのに、サリマのxxはほど遠く、OOは雲のようにつかみどころのないまぼろしに思えた。
xxに行けば、OOが手に入るという掟にそむいて、お金や時間で解決できないなにかを求めているように思えた。
子供達のために働き、その子供達にバカにされ尊厳を傷付けられるのです。
或いは、意志をもって生きる、生きられる人生そのものを手に入れたのだと思います。
私達はそれを、環境や制度のせいにして、結局は自分自信を否定してしまっているのではないでしょうか。
行動が先で結果はそのあとからついてくるものなのだと理解するには、まず労働することを体に覚え込ませなければならなかった。労働で鍛え上げられたいまのサリマならわかる。自分で立ち上がるしかないのだ。
私はこの小説を翻訳小説だと思って読んでいたのですが、それも無理からぬことだったのです。サリマの物語は英語で書かれてもよかったはずなのです。
実際、手紙の主が知人にあてたメ一ルが出てきますが、これはメールそのものが載せてあり、英語です。
手紙の主は英語圏で暮らす日本人であり、英語圏で英語を日常語として使うことを決意した女性なのですから。
しかし、サリマの物語を綴るにあたって、一旦は英語で書き出しますが、母語である日本語を使うことにします。
でもこの小説が描こうとするのは、もっと普遍的な、言語と人間性の問題だったと思うのです。それはサリマの物語だけでは不充分です。
サリマの物語を、何語を母語とする人間が何語で語るのか、そして、何故そうであらねばならないのか、ちゃんと説明する必要があったのだと思います。
しかし、母語を否定したわけでも捨てたわけでもない。
英語で書かれてもよかった。でも、それは母語で書かれなければ、そこに書かれる意味はその半分を喪失してしまう、
なぜなら、母語も第二言語も、周囲の人と意志の疎通を図る意味においては一緒だが、母語とはまた、今日見る夕陽のように、自分にとって特別な意味を持ち得る唯一の言語なのだから、
だからこそ、これは話者の母語で書かれなければならない
作者はそう考えたのではないでしょうか。